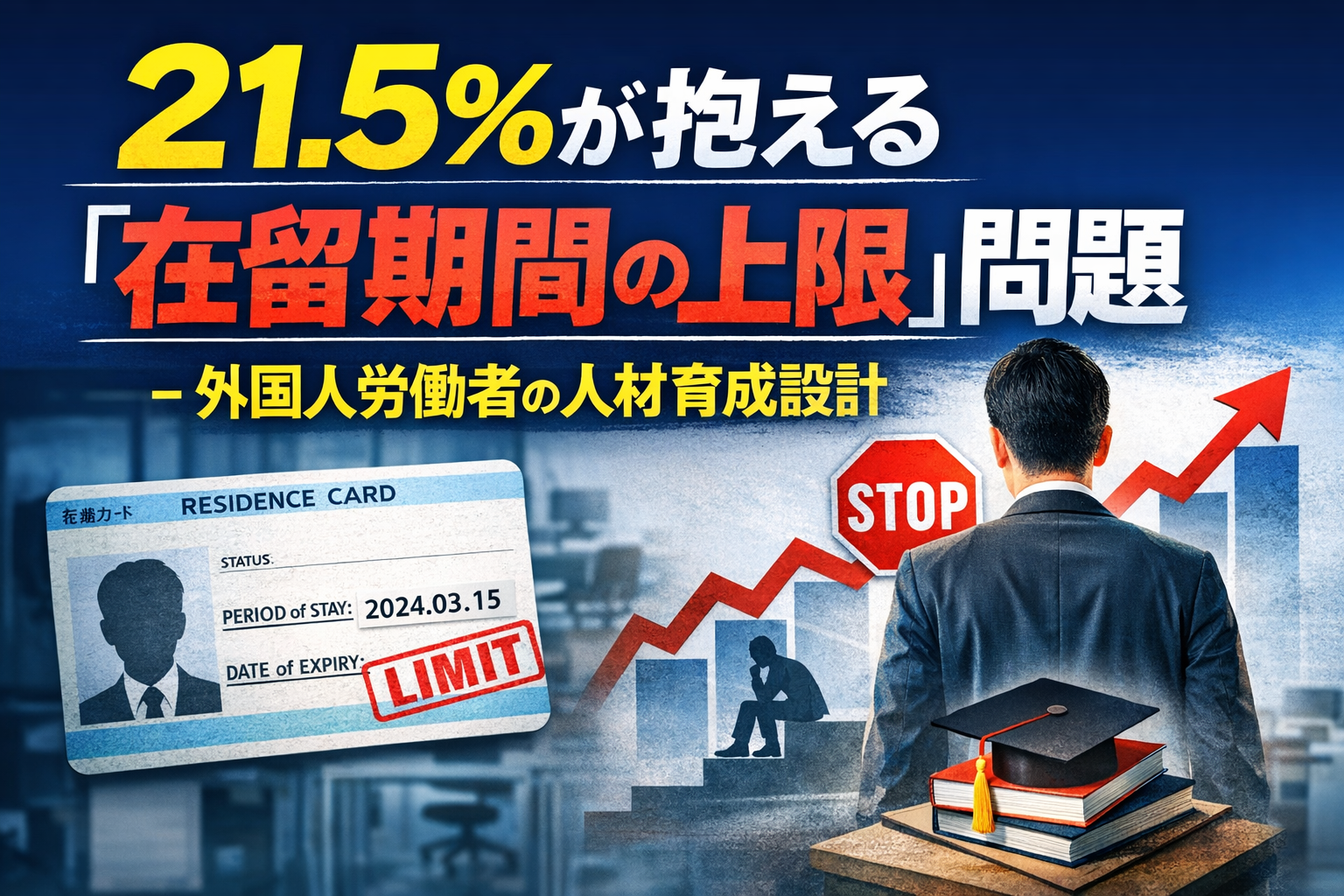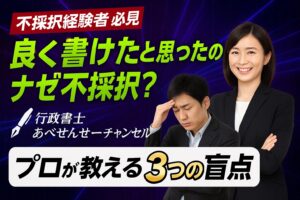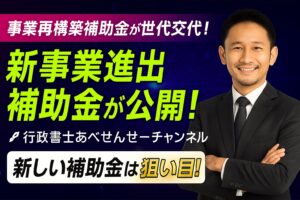【その一文、損してます!補助金に通る“言い換え”のコツ3選】
補助金申請の経験がある方なら、一度はこう思ったことがあるのではないでしょうか。
「内容には自信があったのに……なぜか落ちた」
実際、計画書の中身はしっかりしていたのに、審査で不採択になってしまったという声はよく耳にします。
なぜこうした“もったいない申請”が生まれてしまうのでしょうか?
その答えは、「表現の仕方」にあります。
今回は、YouTubeチャンネル「行政書士あべせんせーチャンネル」で公開中の動画 『その一文、損してます!補助金に通る“言い換え”のコツ3選』をもとに、 読み手(=審査員)に伝わる表現のポイントを、ブログ読者向けにわかりやすく解説していきます。
「伝えているつもり」が落とし穴
補助金申請の計画書は、審査員という“他人”が読む書類です。 自分の頭の中にある熱意や理想が、書類を通して伝わるとは限りません。
つまり、「やりたいこと」ではなく、「なぜそれをやるのか」「それがどう社会に役立つのか」という“伝え方”が重要なのです。
今回紹介する3つのポイントは、申請内容を大きく変えなくても“通る計画書”に近づける実践的な工夫です。
ポイント① 抽象表現は「数字」で言い換えよ
【NG例】「地域の活性化に貢献したい」 【OK例】「年間5回のイベント開催で、前年比20%の集客アップを見込む」
審査員が読みたいのは、「その活動がどれだけの成果を生み出すのか」です。 「活性化」「支援」「強化」などの言葉では、成果の大きさや範囲が伝わりにくく、採点にもつながりにくいのです。
改善のコツは、“数値”や“比較”を盛り込むこと。
売上目標、来場者数、顧客満足度など、可能な限り「見える化」することで、信頼感が増します。
ポイント② 主張ではなく「課題解決」の流れで伝える
【NG例】「最新のPOSレジを導入したい」 【OK例】「現状、会計に1件あたり2分以上かかっており、ピーク時の顧客離脱が発生している。POSレジ導入で決済時間を50%削減し、顧客満足度を向上させる」
単に「導入したい」と言うだけでは不十分です。 「なぜ必要なのか」「どんな課題を解決するのか」まで書くことで、事業の必然性と補助金の意義が伝わります。
補助金は「夢を応援する制度」ではなく、「課題解決の支援制度」。 背景→課題→解決策→期待効果の流れを意識することがポイントです。
ポイント③ 「自社目線」ではなく「利用者目線」で書く
【NG例】「当社は〇〇業界で10年の実績があります」 【OK例】「介護施設でのネイルケア提供で、年間600名以上の利用者に95%以上の満足度を獲得」
自社のすごさを語りすぎると、読み手は「それが何に役立つのか?」と感じてしまいます。
大事なのは、「その事業が、誰のどんな課題を解決するのか」を明示すること。 特に小規模事業者の補助金では、“地域”“高齢者”“子育て世帯”など、支援対象との関連性をはっきりさせることで審査員の共感を得られます。
動画で詳しく解説しています!
この3つのポイントを、実例を交えながらわかりやすく解説している動画はこちら:
▶【その一文、損してます!補助金に通る“言い換え”のコツ3選】 https://youtu.be/yzIyMR746ew
「書いたつもりなのに通らない…」 「審査員に伝わる表現ってどういうこと?」 とお悩みの方は、ぜひご覧ください!
LINE登録で、資料&クイズがもらえます!
📩 今ならLINE登録者限定で、以下の特典を無料プレゼント中!
✅ LDAM特製ガイド「想いに、追い風を。補助金から始める“経営の一歩”」 ✅ クイズ形式で補助金の誤解を解く「9割が誤解している補助金の“常識”」全10問
👉 登録はこちら(1分で完了):https://lin.ee/D6At02N
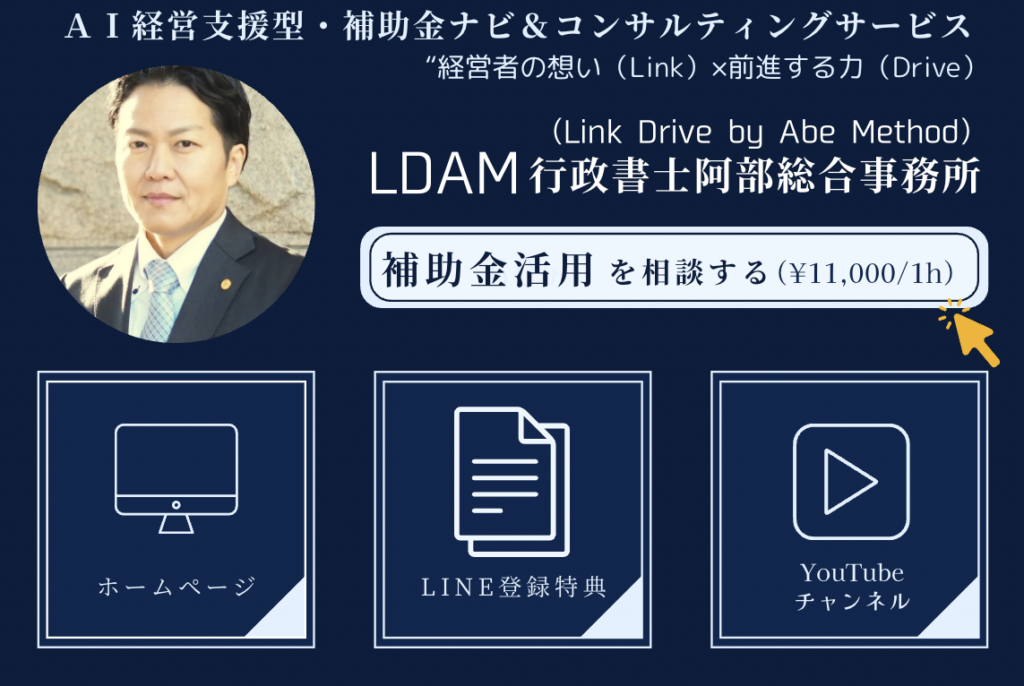

補助金を「資金」ではなく「経営の加速装置」として活かすために。 LINEでしか手に入らない実践資料も、ぜひ受け取ってください。
まとめ|補助金は“書き方”で結果が変わる
補助金申請の計画書は、“伝わるかどうか”が勝負です。
事業の良し悪しだけでなく、
- 数字で見えるか?
- 課題が明確か?
- 利用者に届くか?
この3つの視点で言い換えられているかが、採択率に直結します。
今後の申請の際は、ぜひ今回紹介した3つのテクニックを活かして、 “伝わる計画書”を目指してみてくださいね。
次回の動画ブログもお楽しみに!