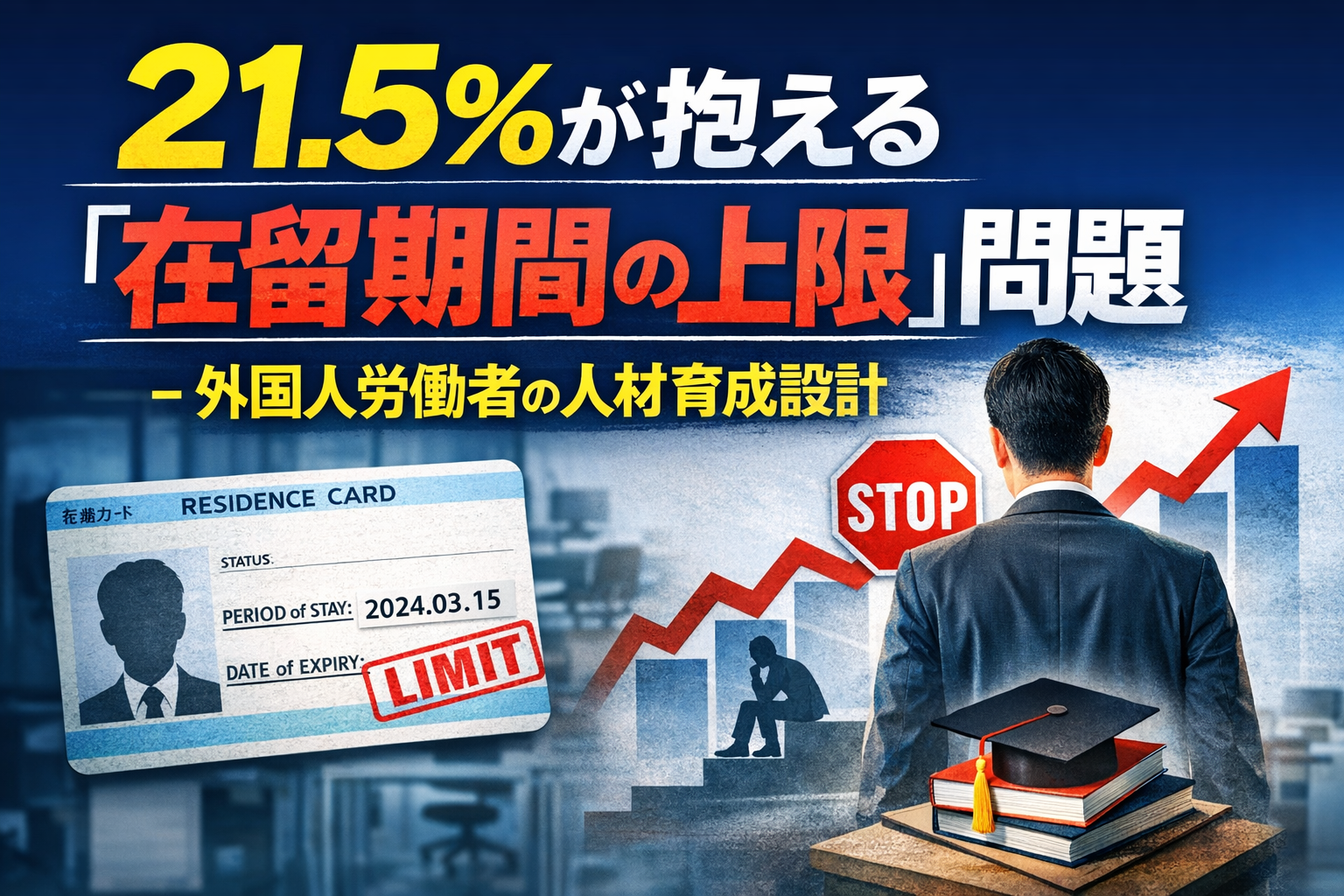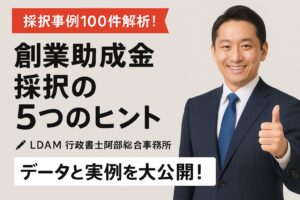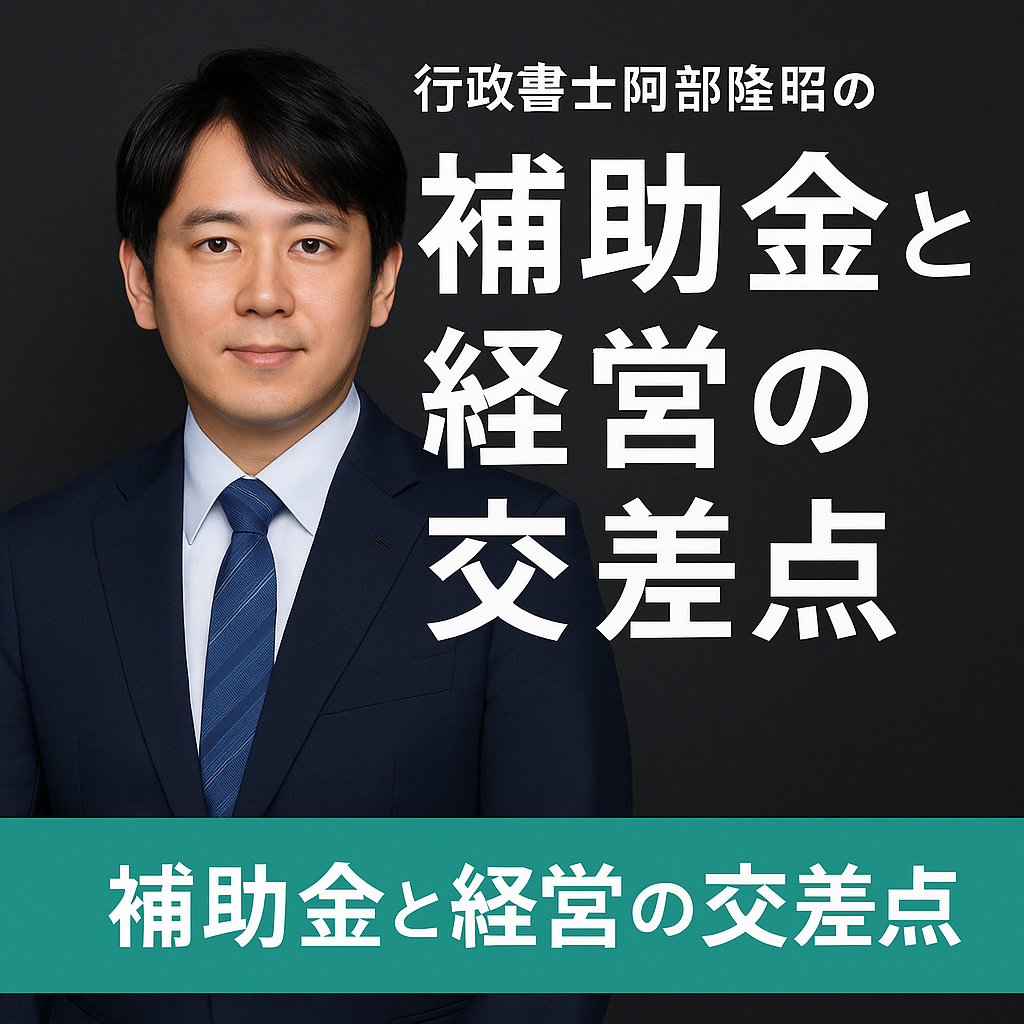東京都創業助成金 採択事例に見る 事業構造の共通点と分析
創業助成金の採択事例を深く分析すると、単に「どんな業種か」や「どんなサービス内容か」だけでなく、事業が持つ**「構造」に共通する傾向**が見えてきます。この「事業の構造」とは、事業の内的な設計図であり、提供価値から収益性、そして社会との接点までを網羅する論理的な骨組みを指します。
まずは、この「事業の構造」が具体的に何を意味するのかを明確にしていきましょう。
「事業の構造」とは何か?
私たちがここでいう**「事業の構造」**とは、単に「何を売るか・どんな業種か」にとどまらず、以下のような複数の要素の関係性と、それらがどのように接続して機能しているかを含んだ、事業の内的な設計図・論理的な骨組みを指しています。
🔧 【定義】事業の構造
「提供価値・対象顧客・仕組み・収益性・接続要素などが、どのように組み合わされて機能しているかの全体像」
🔍 【具体的には】以下のような構成要素を含みます
| 要素カテゴリ | 説明 | 例 |
| 提供価値(Value) | 顧客にとっての本質的な価値 | 時短・安心・共感・承認・文化 |
| 顧客対象(Target) | 誰に届けるのか | 子育て世代/高齢者/中小企業/多国籍人材 |
| 実現手段(Method) | どうやって届けるか(提供形式) | SaaS/訪問/EC/店舗/定期便/体験型 |
| 収益の設計(Revenue) | どうやって持続可能にするか | サブスク/単発/BtoB請負/成果報酬/広告 |
| 接続要素(Connection) | 社会・文化・地域との接続軸 | 環境問題/女性活躍/地方創生/福祉制度/AI |
| トレンド背景構造(Context) | 時代性や制度の流れとの整合 | ポストコロナ/Z世代/インボイス制度/GX文脈 |
🧠 なぜ「構造」で捉えることが重要か?
創業助成金の審査では、単なる「業種」や「サービス内容」だけでは、なかなか審査員の心には刺さりません。審査員は事業の**「再現性・波及性・成長性」**を重視しているためです。
だからこそ、「何と何がどう接続して、どう価値を生んでいるのか?」という構造的な視点が非常に重要になります。この視点を持つことで、あなたの事業計画は次のような強力な説得力を持つでしょう。
🎯 創業助成金においてこの「構造視点」を持つと…
- 「なぜこの事業が今必要とされるのか?」の根拠が明確になる
- 「この事業は、地域や制度とこう接続している」ことを論理的に語れる
- 「この収益モデルだから継続できる」という説得力が出る
さて、事業の「構造」の重要性が理解できたところで、次に具体的にどのような「構造」を持つ事業が創業助成金に採択されやすいのか、その共通傾向を7つの類型に分けて詳しく解説します。各類型において、特に注目すべきは「接続要素」です。
「接続要素」とは?
この構造化分析において「接続要素」とは、その事業の構造が、どのような外部の価値・社会的ニーズ・時代的文脈と接続しているかを示すキーワード群のことです。
🔍 なぜ「接続要素」が重要なのか?
創業助成金の審査では、単に「新しいビジネスかどうか」だけでなく、
- 社会的な意義や背景
- 他の領域とのつながり(教育・福祉・環境・ITなど)
- 地域性や行政施策との整合性
といった「事業が社会とどうつながっているか」が評価の要となります。そのつながり方、つまり「接続の仕方」を分類し、構造の中核にある“外部との接点”を言語化したものが「接続要素」なのです。
✅ 例
| 類型 | 接続要素の例 |
| 社会的信頼の獲得型 | 福祉・制度・地域ケア |
| デジタル拡張型 | 伝統産業 × EC、体験型商品 × サブスク |
| 共創型 | 当事者性、ナラティブ、コミュニティ |
| 業務改善型 | 中小企業、SaaS、自治体業務効率化 |
| ライフスタイル提案型 | ミニマリズム、ジェンダーフリー、生活感覚への提案 |
🌱 応用イメージ
助成金申請書やピッチ資料の中で「接続要素」を意識して記述することで、説得力を格段に高められます。
- 「この事業は”〇〇(接続要素)”に基づく市場ニーズと接続し…」
- 「”地域課題(接続要素)”と接続し、継続的に事業が展開される設計となっている」
といった形で、“つながり”の強さと妥当性を論理的に語れるようになるでしょう。
採択事例に見る 7つの事業構造類型
いよいよ本題です。これまでの分析で明らかになった、創業助成金に採択されやすい事業の7つの構造類型をご紹介します。あなたの事業がどの類型に当てはまるか、ぜひ考えながら読み進めてみてください。
■ 第1類型:社会的信頼の獲得による初動加速型
特徴: 既存の社会課題に対し、制度的・倫理的に「正しい」立ち位置を明確にすることで、信頼性と共感を初期段階から得る構造です。
例: 訪問看護+理学療法、多胎児支援サポート、ペット終末期ケア
接続要素: 福祉・ケア領域、地域連携、家族単位への訴求
期待される効果: 初期から行政・地域コミュニティとの協業が可能になります。
キーワード: 信頼性、制度連携、ケア
■ 第2類型:リアル体験 × デジタル拡張型
特徴: リアルな価値提供(体験・モノ・空間)を基点としつつ、DXやサブスクなどデジタル手法で収益化とスケールを実現する構造です。
例: どら焼き専門×定期便、空き家リノベ×EC販売、体験型ギャラリー+NFT
接続要素: アナログな価値資産 × テクノロジー
期待される効果: 収益モデルの多層化とスケーラビリティが期待できます。
キーワード: リアル資産、デジタル変換、拡張性
■ 第3類型:当事者 × 当事者による共創型
特徴: 創業者自身が課題当事者であり、他の当事者と共に事業を設計・運営する構造です。共感と参加がビジネス資源になります。
例: 発達特性を持つ人の起業支援、LGBTQ当事者によるマッチング支援
接続要素: ナラティブ(物語)、共感型コミュニティ
期待される効果: 口コミや巻き込み力が高く、初期顧客形成が早いのが特徴です。
キーワード: 共創、当事者性、コミュニティ駆動
■ 第4類型:業務改善・構造改革ベース型
特徴: 既存業界や地域にある「非効率」や「属人化」を、SaaS/システム/可視化で解決する実務重視型で、BtoB展開が中心です。
例: 建設業DX、M&A支援クラウド、CO2排出量の見える化
接続要素: 中小企業支援、行政連携、SaaS
期待される効果: 補助金との相性が高く、外部パートナーと連携しやすい傾向があります。
キーワード: 効率化、業務改善、SaaS提供者
■ 第5類型:生活提案・余白創出型
特徴: 既存の消費スタイルや暮らしに対し、提案型の「選択肢」を提供する構造です。感性やライフスタイルへの共鳴が肝となります。
例: ポケッタブル服+サステナEC、観葉植物×ペット安全設計
接続要素: 都市生活者、ミニマル志向、ジェンダー意識
期待される効果: SNS上で拡散性が高く、ブランディングに強みを発揮します。
キーワード: 暮らし提案、ミニマル、選択肢の提示
■ 第6類型:制度創造/仕組み提案型
特徴: 単なる商品・サービス提供ではなく、社会に新しいルール・仕組み・市場の「枠組み」自体を提示しようとする構造です。
例: 副業特化CFOマッチング、日本刀EC+輸出管理支援、宇宙開発の民間連携
接続要素: 制度提案、法律・倫理的フレームの転換
期待される効果: メディア露出や行政との協働のチャンスが高まります。
キーワード: 構造転換、市場創出、制度設計
■ 第7類型:複合価値統合型(領域横断)
特徴: 単一の領域ではなく、「教育×テクノロジー」「福祉×金融」など、異なる2領域以上の価値を融合して設計された構造です。
例: 子育て支援SaaS、地域通貨×健康ポイント、保険×予防医療
接続要素: クロスセクター連携、行政・教育・金融などの橋渡し
期待される効果: 補助金獲得後の事業拡張性が非常に高いのが特徴です。
キーワード: 融合、領域横断、統合価値
🔍 分析総括と示唆
創業助成金では、やはり、”業種ではなく「どんな設計思想でビジネスを組んだか」”、が評価に大きく関与していることがわかります。「制度の文脈」と「共感・体験の文脈」を同時に持つ事業が採択されやすい傾向が見られ、また、巻き込み型・可視化型・拡張型のいずれかをベースに持っていると強いでしょう。
この7つの分類は、創業助成金の申請書を作成するうえで、自身の事業がどの傾向に位置するかを意識しながら、事業を「言語化・構造化」するための強力なフレームとして活用できます。
これらの類型を参考に、あなたの事業計画をさらに磨き上げてみませんか?
もしご自身の事業がどの類型に当てはまるか、または複数の類型を組み合わせる可能性について一緒に相談したい場合には、弊所までご連絡ください。議論したい場合は、お気軽にお声がけください。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭