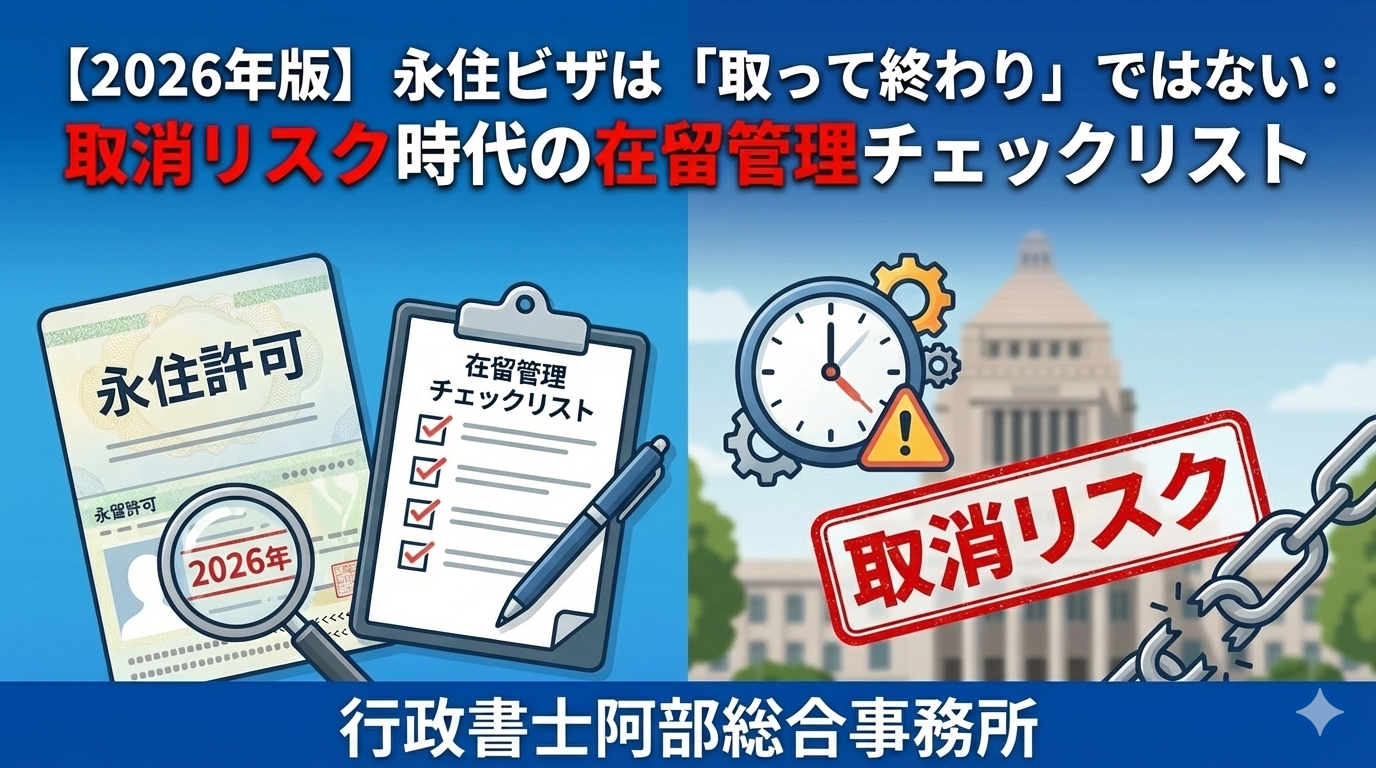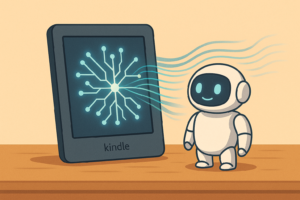コーヒーの香りは、どこで立ち上がるのか?
──全自動から手挽きへ。「構造としての経営」を問いなおす
夜中に淹れる一杯のコーヒーが、思いがけず、私の経営観を変えることになったんです。
それは「道具を変えただけ」の話。なのに、結果として「見える世界」がまるで違ったんです。
◆ 全自動をやめた夜
長らく私は、全自動のコーヒーマシンを使っていました。
豆をセットすれば、あとは勝手に挽かれ、お湯が注がれ、香り高いコーヒーが数分で出てくる。手軽で、均質で、スピーディー──まさに“効率の象徴”でした。
でもある夜、ふと気になったんです。
深夜に仕事を終えた静寂の中で、全自動の「ガリガリガリ……」という豆を挽く音が、やけにうるさく感じたんです。
「さすがにこれは、憚られるな」と思った私は、全自動をやめ、手挽きのミルとハンドドリップに切り替えました。

◆ 音が静かになったら、“香り”が聞こえてきた
手で豆を挽くと、不思議とその音、”ガリガリ”が心地いいんです。
何より驚いたのは、「あれ、コーヒー豆って、挽いてる時からこんなに香ってたんだ?」という体験でした。
全自動の頃には気づけなかった、“香りが立ち上がる瞬間”を自分の手の中で感じることができたんです。
つまり私は、効率と引き換えに、大事な感覚の層をまるごと取りこぼしていたんですね。
しかもこの静かな手挽きスタイルなら、深夜でも気兼ねなくコーヒーが淹れられる。周囲に配慮しながら、自分に自由を許す構造に切り替えられたわけです。
◆ これは経営の話でもある
この変化を体験してから、私はふと「これはまるで、経営の構造そのものだな」と感じるようになりました。
全自動マシンは、いわば非介入型・効率最優先の経営モデルです。
- 現場のプロセスには立ち入らず
- 一律で安定的な結果を求め
- “音”や“香り”はシステムに吸収されて見えなくなる
それは一見、スマートで洗練されています。でも、人や組織が何かを「感じる余白」や「立ち止まる余地」は、失われがちです。
一方で、手挽きは関与型・体験重視の経営モデル。
- 自ら手を動かすことでプロセスと向き合い
- 香りや手応えという“見えない価値”を回収し
- 周囲との調和を意識しながら、自分のリズムで進める
ここにあるのは、「早く終わらせること」ではなく、“プロセスそのものが価値になる”という感覚の設計です。
◆ 経営における「香り」とは何か?
私は今、コーヒー豆を挽きながら考えます。
経営における“香り”とは、たとえば
- 顧客の声がふと社内に届いたときの空気の変化
- 現場で働くスタッフがある言葉にうなずいた一瞬
- 組織の誰かが、自発的に新しい問いを立てた瞬間
そういった、数値やKPIでは測れないけれど、確かに立ち上がる“気配”や“兆し”のことではないでしょうか。
もし私たちの経営が全自動すぎて、そこに関与することなく「結果」だけを追い求めていたら、香りが立ち上がる瞬間には、きっと気づけないんです。
◆ 効率の中に“静けさ”を設計する
この気づきの先にあるのは、単なる「効率 vs 感性」ではありません。
むしろ、「効率の中に、静けさと香りを共存させる構造をどう設計するか?」という問いなのだと思います。
私は、手挽きにしてよかったと思っています。それは、コーヒーがおいしくなったから、というよりも、「感じる力」を取り戻す構造に変えた自分を、信じられるようになったからです。
◆ あなたの組織に「香り」を取り戻す具体的な一歩
では、あなたの組織ではどうすれば「香り」を感じられるようになるでしょうか?
具体的な一歩として、例えばこんなことを試してみてはいかがでしょう。
- 「ノー残業デー」ならぬ「非効率探求デー」を設ける: 普段は効率重視の業務も、週に一度だけ「なぜこのプロセスなのか?」「もっと良い香りが生まれる方法はないか?」とチームで深く議論する時間を作る。
- 顧客の声を聞く「オフライン時間」を増やす: アンケートやデータだけでなく、顧客と直接対話する非公式な場を設け、数値には現れない「生の声」や「感情の揺れ」に触れる機会を作る。
- 現場の「つぶやき」に耳を傾ける仕組みを作る: 定期的なミーティングとは別に、現場で働くスタッフが気軽に意見や気づきを共有できる匿名ボードや休憩室での雑談タイムを設ける。
◆ 最後に
経営において、私たちは多くの場面で「全自動」になりすぎます。それは悪いことではないのですが、香りを失った経営は、長くは続きません。
あなたの組織には、どこに香りが立ち上がっているでしょうか?
その気配を感じられる時間と構造を、もう一度デザインしてみてはいかがでしょうか。きっとそこに、今まで見えなかった本当の価値が、ふっと香ってくるはずです。
行政書士阿部隆昭