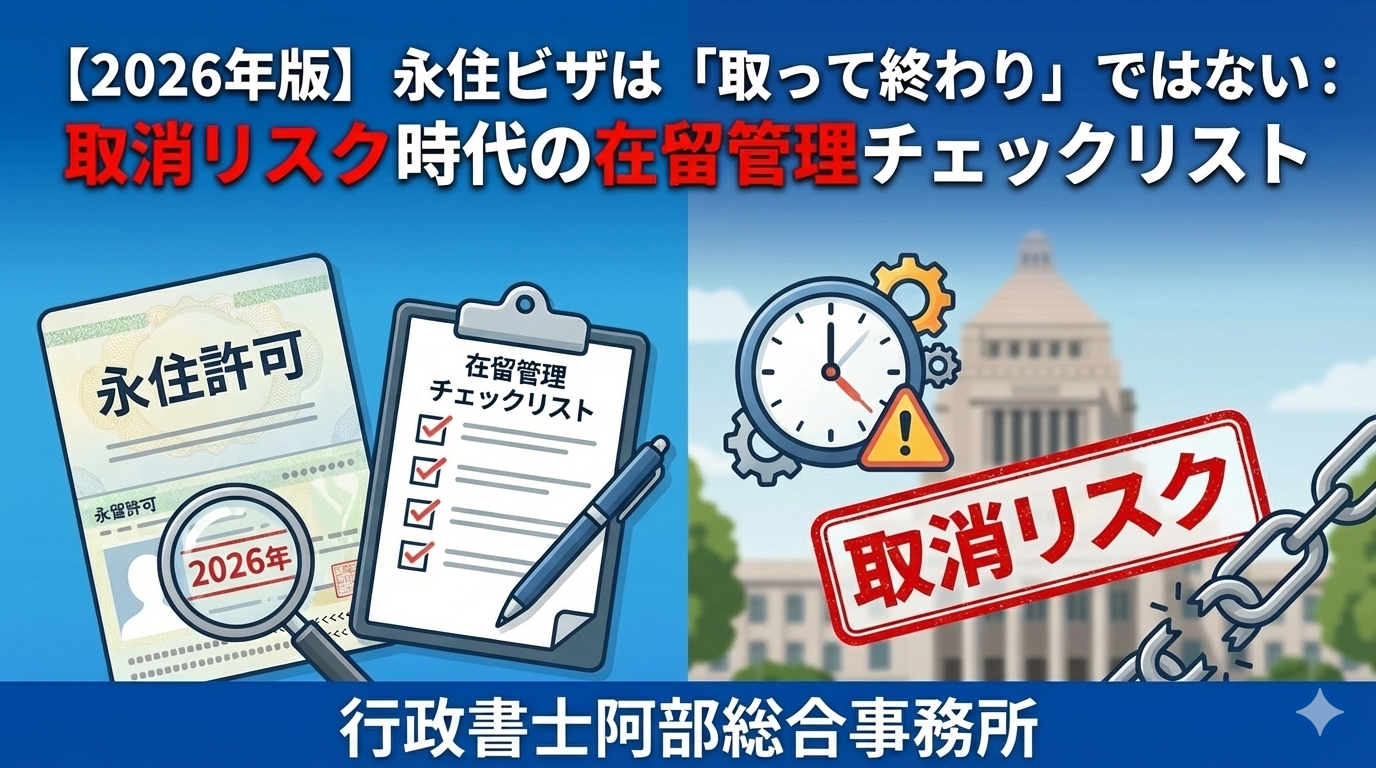📘 【最終回】外国人材の「使い捨て」を終わらせる10年戦略
制度は変わる。その先に必要なのは、人を“選ぶ”社会から人と“つながる”社会への覚悟だ。
これまでの連載で、技能実習制度が抱える課題と、それらを解決するために生まれた新制度「育成就労」について解説してきました。この制度は、単なる「働くための仕組み」から「共に育ち、共に暮らす仕組み」へと、日本の外国人材制度を大きく変えようとしています。
しかし、その未来を持続可能なものにするには、法律を変えるだけでは不十分です。私たちは、外国人材が日本で安心して生活し、家族と暮らせる「共生インフラ」を再設計する必要があります。なぜなら、その環境こそが、長期的な人材の定着と企業の成長を約束するからです。

## 離職・失踪の「自己責任」論はもう古い
技能実習制度において、失踪者数が後を絶たなかったのは、個人の問題ではなく、制度の構造的な問題に起因しています。来日前の虚偽説明、不透明な費用、言葉の壁による孤立など、様々な要因が複雑に絡み合い、多くの外国人材を追い詰めてきました。
育成就労制度では、これらの構造を是正するため、「転籍の自由」「費用制限」「通訳支援」「監理体制の透明化」といった具体的な改善策が盛り込まれています。しかし、どれだけ制度を整えても、彼らを「社会の枠外に逃げた犯罪者」と見なすような意識が変わらなければ、真の解決には繋がりません。
企業が「なぜ、彼らは失踪したのか」という背景にある構造的な孤立に目を向け、共に解決しようとする姿勢こそが、新しい制度を機能させる鍵となります。
## 「定着」の先にある、企業の未来戦略
外国人材が日本で長く働きたいと思えるかどうかは、**「定着を支える実務」**にかかっています。
育成就労制度は、3年間の就労を経て、特定技能1号、さらに特定技能2号へとステップアップできる道を開きます。これにより、外国人材は日本でのキャリアを長期的に見据えることができます。
しかし、この制度が絵に描いた餅で終わらないためには、企業と地域社会が連携して、以下の課題をクリアする必要があります。
- 永住・家族帯同のサポート: 永住申請は複雑な手続きが必要です。申請書類の不備や要件の誤解で、せっかく優秀な人材が日本を離れることのないよう、専門家によるサポートが不可欠です。
- 生活インフラの整備: 外国人材が安心して暮らせるよう、地方自治体や地域と連携し、子どもの教育や福祉に関する情報提供を行う必要があります。
これらは単なる「支援」ではありません。優秀な人材に「この会社なら将来も安心だ」と確信させ、長期雇用へと繋げるための重要な投資なのです。
## 専門家が担う「現場と制度をつなぐ」役割
育成就労制度の施行に伴い、外国人材を支援する「監理支援機関」の在り方も大きく変わります。従来の登録制から「許可制」となり、監督と評価が可能になります。
しかし、制度がどれだけ整っても、現場の企業と外国人材の間には多くの課題が残ります。
- 制度は理解したが、現場でどう運用すればいいかわからない。
- 言葉の壁を越えて、外国人材の悩みに寄り添う時間がない。
- 日常生活で発生するトラブル(病院への付き添い、子どもの就学相談など)にどこまで関わるべきか分からない。
これらの課題を解決するためには、企業・監理機関・行政の間を埋める専門家の存在が不可欠です。
行政書士阿部総合事務所では、在留資格制度に精通する行政書士として、以下の支援を提供しています。
- 法的支援: 在留資格の更新や永住申請といった入管手続きを、正確かつ円滑にサポートします。
- 運用支援: 複雑な雇用契約書や育成計画を多言語化し、企業と外国人材双方が内容を理解できるようにサポートします。
- 共生支援: 入管手続きの枠を超え、外国人材の生活におけるトラブルや相談にも対応し、企業と地域が連携して彼らを支える体制づくりを支援します。
制度は、現場で運用されてこそ意味を持ちます。当事務所は、単なる書類上の手続きだけでなく、外国人材が安心して働ける「現場」を共に創るパートナーでありたいと考えています。
## 最後に──「選ばれる」企業から「つながる」企業へ
育成就労制度は、企業にとって「優秀な外国人材に選ばれる」ための競争が激化することを意味します。しかし、それは決してネガティブなことではありません。
外国人材のキャリアや人生を真剣に考え、共に歩む覚悟を持つ企業こそが、これから先の時代を生き抜くことができます。
外国人材を「助けてあげる側」ではなく、共にこの国の未来をつくる「当事者」として迎える覚悟。それこそが、新しい制度を最大限に活用し、企業価値を高めるための最も確実な戦略となるでしょう。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭